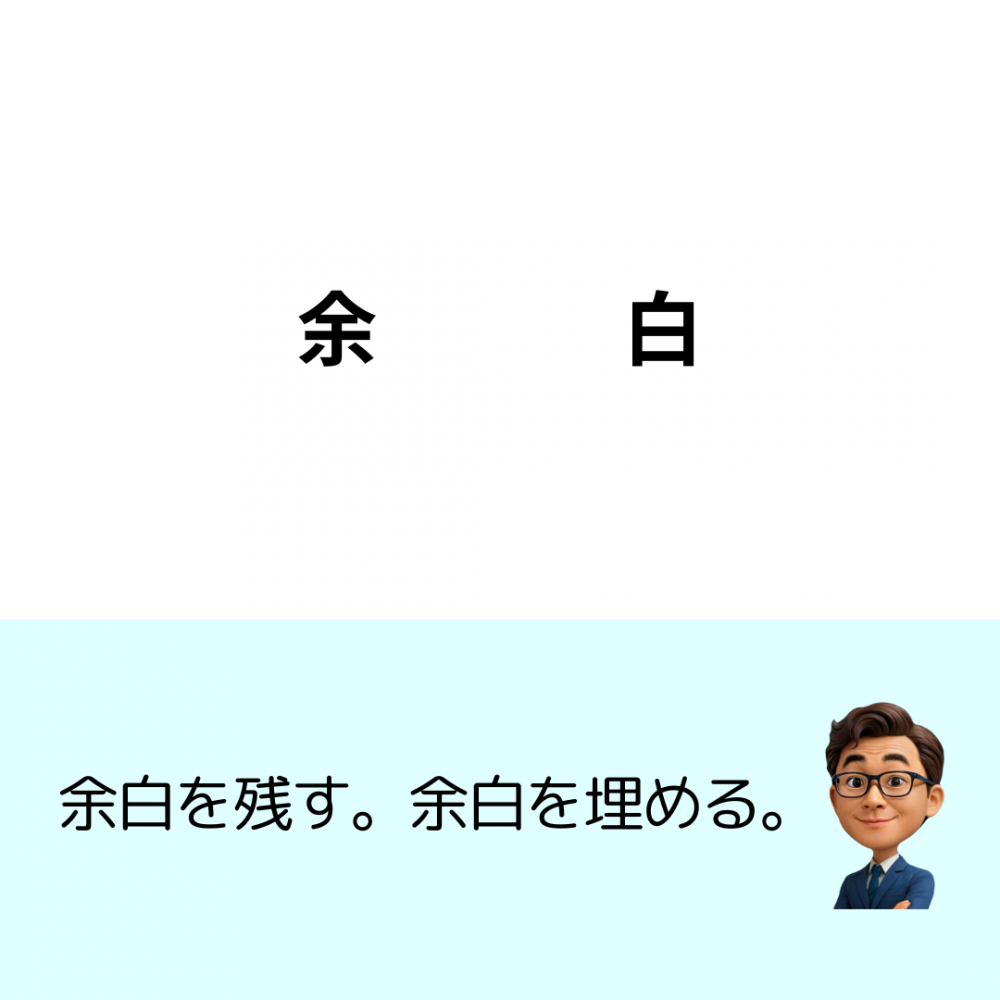□■□□■小山国語教室からお知らせ■□□■□
小山国語教室では、2025年度の各講座の体験授業の申込を受付中!
詳しくはこちらのページへ!ぜひご覧ください!
↓↓↓
「夏の国語特別指導」が始まっています!
詳しくはこちらのページへ!ぜひご覧ください!
↓↓↓
□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■
こんにちは。
当教室では、小学生に俳句、詩の作成指導をしています。
初めは抵抗や苦手意識を持っていても、指導を進めていくうちに、とても楽しくなるようです。
そして、彼らの作品を読んでいると、よくできているなといつも感心してしまいます。
大人よりも小学生の方が案外上手に作ることができるのかもしれません。
それはなぜでしょうか。
大人になればなるほど、「相手に伝わるように明確に書かなければならない」という考えがあるため、
使える文字数に限りがある韻文について、堅苦しい作品が仕上がってしまいがちです。
一方、小学生は明確に伝えるなんてお構いなし。使える文字数だけを気をつけながら、とりあえず作品を仕上げるのです。
確かに、コミュニケーションであれば、相手に伝える、分かってもらうことを第一とするので、明確な表現が必要となります。しかし、それだけでは、コミュニケーションの幅が狭まってしまうかもしれません。多少の余白を残すことも多いに必要になるかもしれません。
話はずれてしまいますが、私が大学院生だった当時、とある先生がこんなことを仰いました。
「レジメには余白を作っておきなさい。余白があると、聞いていて思考する余裕ができるんだよ。」
細々と説明が並ぶだけでは、自分の思考をはさむこともできず、ただ内容が頭の中を流れていくだけになってしまいます。多少の余白を残すことで、「これは一体何かな?」と思考をはさむことができるのです。
となると、文章を読むという行為は、読みながら思考をはさむ行為となります。余白とは行間です。自分が持ち合わせている知識、事実、あるいは経験などをはさみながら、思考をもって文章と向き合う行為が、文章を読む、あるいは文章読解ということになるのかもしれません。
「答えはどこに書かれているか。探してみよう。」
そんな国語の授業は、思考を育てる国語の授業には到底なりえませんよね。
思考を促す授業をいかに展開していくか。これこそが国語の専門教室の重要は役割であるのです。
そこで培われた力こそ、子どもたちが社会生活の中で本当に必要とされる読解力に他ならないのです。
余白を残す文章作成。余白を埋める文章読解。
少し試してみませんか?