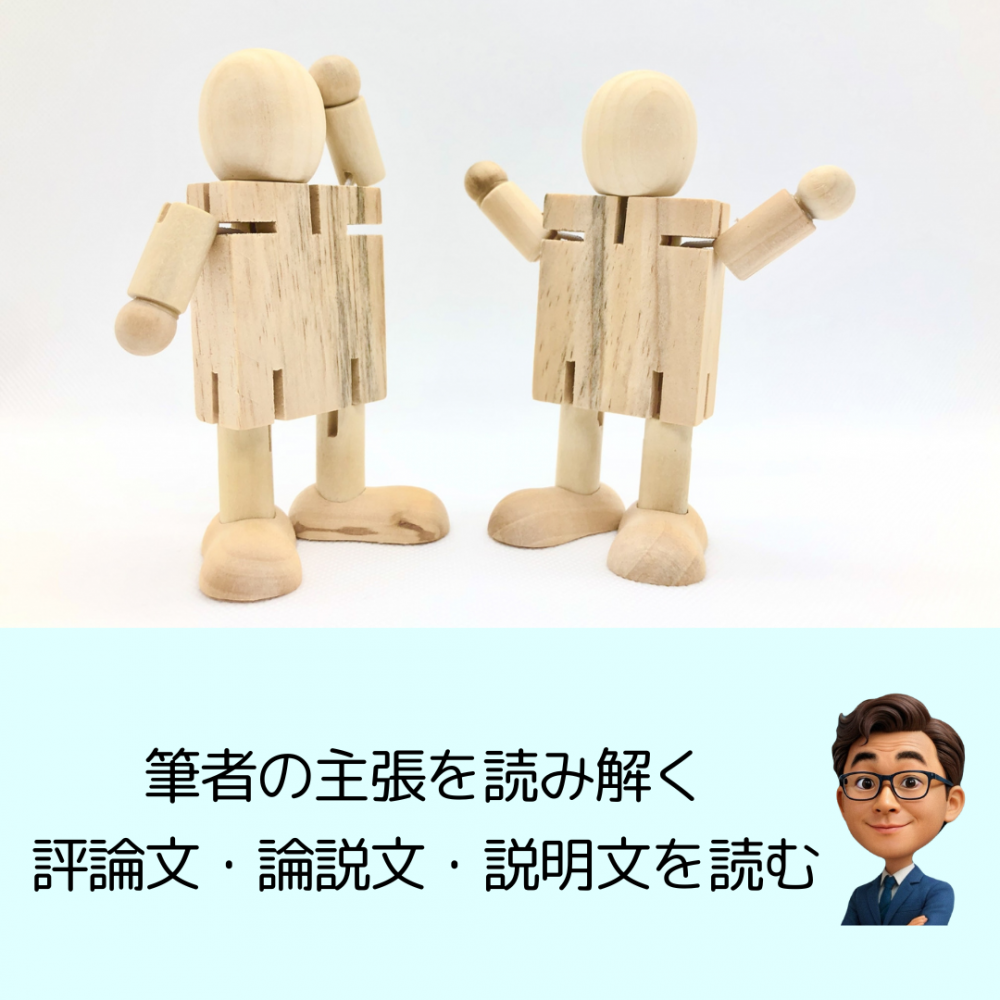□■□□■小山国語教室からお知らせ■□□■□
小山国語教室では、2025年度の各講座の体験授業の申込を受付中!
詳しくはこちらのページへ!ぜひご覧ください!
↓↓↓
「春の国語特別指導」の実施中!
詳しくはこちらのページへ!ぜひご覧ください!
↓↓↓
□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■
こんにちは。
さて、突然ですが、世の中には「お説教」と呼ばれる行為があります。
長々とした「お説教」を聞かされたことがある人も数多くいることでしょう。
そんな長々とした「お説教」をする人が言いたいことをまるで分からないという人もいるのも事実ですが、
大概の場合、「わかったよ。そうすればいいんだろ!」と半ば苛立ちながら反発したり、心中で歯向かったりしているのではありませんか?
その「お説教」の中身をのぞいてみましょう。
多くの場合、個人の経験であったり、周りの様子からの個人の感想であったり、時には、客観的な知識・道理であったりが「お説教」の大部分を占めているはずです。「わかったよ。もういいよ。」と思ってしまう今日この頃ですよね。
この「お説教」、話している側は自分なりの「論理」つまり筋道を立てて伝えているのです。
「私が子どもの頃はね、・・・・だったの。分かる?だから、ーーーーしないとだめじゃない。」
「ほら、周りを見てみなさい。・・・・・でしょ。だから、ーーーーーなのよ。」
表現の違いがあれ、いずれにしても、立論はこんな感じです。
「だから、何だってんだよ。」「自分はそんなんじゃないんだよ。」と歯向かいたくなる気持ちも十分に分かりますが、そこをぐっとこらえて、「はいはい、わかりました」としてみてはどうでしょう。なんか、相手の言っていることが分かった気がしませんか?
上記の「お説教」を「評論文・論説文・説明文」と置き換えてみてください。
長々と根拠となる事実や知識などを列挙して「ほら、だからーーーーなんだよ」、あるいは「ねえ、〇〇〇について考えたことある?いろいろ調べてみるとね[いろいろ考えてみるとね]、どうも・・・・・なようだよ。だからーーーーーってことなんじゃないかな。」という話に落ち着ていくるのです。そうすると、筆者が言いたいことって、結局、大したことではない、そんなこと知っているよ、ということに落ち着いてくることに気づいてきます。
要するに、「評論文・論説文・説明文」を読むというのは、書き手が伝えたい長い「お説教」(と言ったら筆者に失礼なのですが…)にお付き合いしていくことであり、またそのお説教を納得していくことなのです。「そんなのちがうよ。」「そんなこと知るかよ。」と歯向かってしまうことではないのです。(それをするのであれば、もっとたくさん勉強して、大学・大学院で議論を戦わせてください。)
筆者の主張を読み解く。それは筆者が熱心に伝えようとする思いをくみ取ることです。そこに必要なことは、案外、素直を話を読んであげる姿勢なのかもしれませんよ。